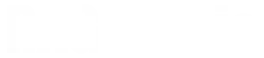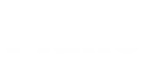【祝!発表会デビュー】初めてのピアノ発表会におすすめの曲を紹介
ピアノ教室に通う方の大半が経験する「発表会デビュー」。
初めてのピアノ発表会には、誰もがワクワクした気持ちと同時に緊張や不安を抱えながらチャレンジするものです。
発表会の曲は先生が提案してくれる場合もありますが、「これを弾いてみたい!」と思う曲があれば、積極的に提案してみるのもアリ!
この記事では、初心者から初級者向けの発表会におすすめの作品をたっぷりご紹介します。
「メリハリのある子供向けの短い曲」「みんなが知っている発表会の定番曲」「初心者の大人向けのピアノ曲」など、発表会デビューにピッタリの曲を集めましたので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
- 【6歳児向け】ピアノ発表会で映えるおすすめ楽曲をピックアップ!
- 【初級編】発表会で弾きたいおすすめのピアノ曲まとめ
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【4歳児向け】ピアノ発表会におすすめの楽曲をピックアップ!
- 【幼児のピアノ曲】発表会で弾きたい!華やかなおすすめ作品を厳選
- 【初級者向け】やさしい&弾きやすい!ピアノ発表会で聴き映えする曲
- 【ピアノでディズニーの名曲を】発表会にもおすすめの簡単な楽曲を厳選
- ピアノをはじめた初心者におすすめ!大人も楽しめる楽譜10選
- 【ピアノ発表会】男の子におすすめ!かっこいい&聴き映えする人気曲を厳選
- 【小学生2年生向け】ピアノの発表会で弾きたい!おすすめの名曲&有名曲
【祝!発表会デビュー】初めてのピアノ発表会におすすめの曲を紹介(101〜120)
となりのトトロ久石譲

ジブリ作品を担当し、いくつもの名曲を作り上げてきた日本の作曲家、久石譲さん。
クラシックやピアノ曲に詳しくない方でも知っている、非常にポピュラーな作曲家ですね。
そんな久石譲さんの作品のなかでも、特に6歳児にオススメしたい作品が、こちらの『となりのトトロ』。
小学校にピッタリな明るい曲調が印象的な作品で、一定のテンポのため、非常に弾きやすい特徴を持っています。
そういった作品でありながら、裏拍も学べる楽曲なので、良い経験にもなるでしょう。
チューリップ井上武士

いくつもの童謡を作り上げてきた日本の作曲家、井上武士。
こちらの『チューリップ』はそんな彼の作品のなかでも、最も有名な楽曲です。
ピアノにおけるこの作品の難易度は非常に低く、始めたての子どもでも取り組めるレベルです。
始めてのピアノ発表会にはうってつけの楽曲と言えるでしょう。
動画のようなアレンジは両手に慣れていなくても取り組みやすく、キャッチーな作品であることから聴き映えもします。
ぜひチェックしてみてください。
ひよこのワルツCatherine Rollin

まるでひよこがダンスを踊っているようなかわいくて明るい曲。
この曲は『ビーニー動物園』という曲集に収められているのですが、この「ビーニー」というのはアメリカの動物のぬいぐるみのことです。
手のひらサイズで日本のお手玉のように中に豆が入っています。
そんな小さな動物たちが織りなす世界を想像しながら演奏したいですね。
曲の冒頭は左手がメロディー、中間部は右手がメロディーなので、伴奏が大きくなりすぎないようにバランスに注意しながら演奏しましょう。
こども音楽会 Op.210 第7曲「狩りの曲」Cornelius Gurlitt

子供らしいかわいらしさにあふれたコルネリウス・グルリットのピアノ曲集『こども音楽会 Op.210』。
第7曲『狩りの曲』は、小さな子供が野原を駆けまわっている様子を連想させるような、快活で明るい1曲です。
軽やかなスタッカートや音の粒をそろえて弾く連符、2音間のスラーなど、基本的なテクニックも含まれているため、発表会で立派に演奏できれば、これからピアノを続けていくうえでの大きな自信につながるはずです!
スケルツィーノGeorg Philipp Telemann

1681年生まれのゲオルク・フィリップ・テレマンは、特に18世紀前半においてドイツやフランスで絶大な人気を誇り、クラシック音楽史上において最も多くの作品を作った作曲家としても知られている偉大な存在です。
86歳と当時としては非常に長生きしたことや、ヘンデルやバッハとの交流も有名ですね。
そんなテレマンの作品は日本でも大いに親しまれていますが、今回は陽気で楽しげな雰囲気と、右手と左手がどちらも旋律を奏でることが特徴的な『スケルツィーノ』を取り上げます。
初級の方は右手と左手の独立した動きや細やかな運指などにやや戸惑うかもしれませんが、技術的に難しいことはありませんし十分対応できるはず。
中間部の同じ音を連打する際の左手の力加減には注意して、あくまで軽やかに表現するようにしましょう。