ラフマニノフの名曲。おすすめのラフマニノフの曲
ロシアを代表とする作曲家の一人セルゲイ・ラフマニノフ。
同じロシアの作曲家チャイコフスキーに才能が認めながらも一度は音楽を挫折したこともあるラフマニノフ。
そんな心境と環境で生み出されたからか現代人にも通じるものがあり、切なくて儚い、時には熱情的な作風は聞いた人全員を虜にします。
今回はオーケストラで演奏される交響曲から声楽、ピアノ曲までセレクトしました。
知らない曲を聞いても「あ!
ラフマニノフだ」と思うのではないでしょうか。
ぜひ聴いてみてくださいね。
- 【超上級】上級者でも難しい!難易度の高いピアノ曲を厳選
- 【難易度低め】ラフマニノフのピアノ曲|挑戦しやすい作品を厳選!
- シベリウスの名曲。人気のクラシック音楽
- 【上級】弾けたら超絶かっこいい!ピアノの名曲選
- 【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- ロベルト・シューマン|名曲、代表曲をご紹介
- ボレロの名曲。おすすめのボレロ形式の人気曲と名演
- 【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- アレクサンドル・ボロディンの名曲。人気のクラシック音楽
ラフマニノフの名曲。おすすめのラフマニノフの曲(31〜40)
『幻想的小品集』より第1番「悲歌(エレジー)」Sergei Rachmaninov

ロシアが生んだ世界的な作曲家にしてピアニスト、セルゲイ・ラフマニノフが手掛けた作品の持つ旋律は、美しくも悲哀にあふれたものが多いですよね。
今回の記事で紹介するのにふさわしいラフマニノフ作品は多く存在していますが、本稿で取り上げているのは1892年にラフマニノフが手掛けたピアノ独奏曲集『幻想的小品集』の第1曲『悲歌』です。
第2曲『前奏曲』の方が知名度という点では勝るかもしれませんが、こちらの作品が持つ旋律の美しさや切なさも素晴らしく、左手でつむがれるアルペジオのフレーズを軸としながら流麗かつメランコリックに展開していく様は実に美しいですね。
このような楽曲を19歳という若さで完成させたラフマニノフの才能たるや、恐るべしとしか言えません……。
13の前奏曲 Op.32 第5番 ト長調Sergei Rachmaninov

セルゲイ・ラフマニノフが1910年に完成させた13曲からなる『13の前奏曲 Op.32』。
演奏活動で多忙を極める中、落ち着いたタイミングで短い期間で作曲された作品とされています。
『第5番 ト長調』は、長調でありながらどこか不安定さも感じさせる左手の伴奏の上に、穏やかなメロディが重なった繊細な1曲です。
長いトリルや細かく動くパッセージの音の粒をそろえ、にごりのないよう、音質にこだわって練習しましょう。
2台のピアノのための組曲第2番「タランテラ」Sergei Rachmaninov

ラフマニノフのキラキラ感を常にまといながらも力強さと厚みを併せ持つクールかつ情熱的な曲です。
曲の始まりからひきつけられることまちがいなしです。
ラフマニノフは交響曲第1番の初演失敗後しばらく落ち込んで作曲できない時期が続きました。
この曲はその後、立ち直りはじめた頃の作品です。
『14の歌曲集』第14曲「ヴォカリーズ」Sergei Rachmaninov
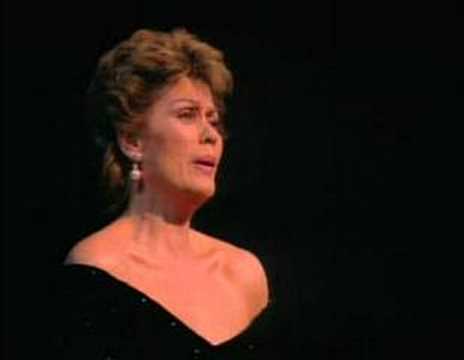
ヴォカリーズは主に発声練習のときに用いる「アー」など母音のみによって歌う歌唱法で、このラフマニノフの曲にも歌詞がありません。
はじめは独唱とピアノ伴奏でしたが、自ら管弦楽版を作りました。
ピアノ独奏版、チェロやヴァイオリンなどの独奏楽器とピアノ伴奏によるデュエット版がなどさまざまな編曲がされています。
編曲版では、ホ短調に移調されていることが多い作品です。
ピアノとオーケストラのための「パガニーニの主題による狂詩曲」より 第18変奏Sergei Rachmaninov

ピアノとオーケストラのために作曲された名作です。
ニコロ・パガニーニの『24のカプリース』をもとに、24の変奏が繰り広げられます。
特に第18変奏は、優美で魅力的な旋律と和声で多くの人を魅了している人気の高い1曲!
ラフマニノフさんは1934年夏、スイスの自宅でたった7週間で本作を完成させました。
1934年11月、フィラデルフィア管弦楽団とともに初演し、演奏前にクレーム・ド・メンテを飲んで緊張を和らげたそうです。
和音の中のメロディラインを意識的に響かせながら、穏やかにかつロマンティックに演奏したい方におすすめの曲ですね。
ラフマニノフの名曲。おすすめのラフマニノフの曲(41〜50)
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 Op.18 第2楽章Sergei Rachmaninov

セルゲイ・ラフマニノフが協奏曲作曲家として広く知られるきっかけとなった『ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 Op.18』。
激しい第1楽章とは打って変わって、この第2楽章は祈りのような穏やかで崇高な雰囲気が印象的で、ピアノ部分だけを切り取ってもうっとりするような美しさを味わえます。
ラフマニノフによるピアノ独奏版はありませんが、さまざまなアレンジの楽譜が出版されていますので、自分のレベルに合ったものを選び、なめらかに流れるメロディとラフマニノフらしい和声の移り変わりを楽しみながら弾いてみましょう。
幻想的小品集 作品3-2「前奏曲」Sergei Rachmaninov

『鐘』という名で有名な、ロシア出身のセルゲイ・ラフマニノフが19歳の頃に作曲したピアノ曲。
彼の代表曲の一つです。
冒頭の重厚な和音がまるで鐘の音のように鳴り響き、おどろおどろしい雰囲気はハロウィンにぴったり!
中間部では激しい三連符が不安と緊張を高め、ゾクゾクするような気分にもなります。
欧米では「モスクワの鐘」の愛称で親しまれ、ラフマニノフの演奏会では必ずアンコールで求められたそう。
ハロウィンパーティーのBGMや、怖い話をする時の伴奏にもいかがでしょうか?
本作を聴けば、きっと特別な雰囲気を味わえるはずです。


