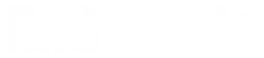フランツ・リストの名曲。人気のクラシック音楽
ハンガリー出身でドイツやオーストリアなどヨーロッパで活躍したフランツ・リストの名曲たちを紹介します。
「ラ・カンパネラ」「愛の夢」などの名曲で知られるピアニスト、そして作曲家でもあったリストの作品の中から、ピアノ曲はもちろんオーケストラで演奏する交響曲を含めておすすめする名曲、代表曲をご紹介します。
どんな曲でも初見で弾きこなしたという逸話があることから「ピアノの魔術師」と呼ばれた作曲家の素晴らしき名曲の数々をお楽しみください。
フランツ・リストの名曲。人気のクラシック音楽(101〜110)
巡礼の年 第2年 第2曲『物思いに沈む人』Franz Liszt

フランツ・リストがイタリアを旅行した際に触れた、絵画や文学などの芸印象を音楽に表したとされているのが、『巡礼の年 第2年』の全7曲。
第2曲『物思いに沈む人』は、葬送曲のような重々しく静寂な曲調の作品です。
演奏する際には、オクターブの重音や和音を十分に体重を乗せて響かせ、音に深みを持たせることが大切です。
一説によると、この曲はダビデ像などで有名な彫刻家であるミケランジェロが手掛けた彫像からインスピレーションを受けているのだそう。
ミケランジェロの彫刻を見てから想像を膨らませてから演奏するとよいかもしれません。
巡礼の年 第2年への追加「ヴェネツィアとナポリ」S.162 第3曲「タランテラ」Franz Liszt

フランツ・リストの集大成といっても過言ではない作品『巡礼の年 第2年への追加「ヴェネツィアとナポリ」S.162 第3曲「タランテラ」』。
20代から60代までに断続的に作られた作品で、ロマン主義から印象主義へ移り変わる様子が味わえます。
そんな本作は、フランツ・リストの作品というだけあって、高い難易度をほこります。
細かい装飾音が連続する部分が非常に難しいのですが、ここは高い演奏効果を発揮する部分でもあるため、聴いてる分には非常に魅力的な作品です。
愛の夢 第2番『私は死んだ』Franz Liszt

フランツ・リストの『愛の夢』といえば、フェルディナント・フライリヒラートの詩『おお、愛しうる限り愛せ』に曲をつけた第3番が有名ですが、ドイツの詩人ルートヴィヒ・ウーラントの詩に曲をつけた第2番『私は死んだ』も、非常に美しい隠れた名曲です。
流れが美しい第3番と異なり、切々と思いをかみしめるように進んでいくのが、第2番の特徴的な部分。
音1つ1つの響きを意識しながら弾いていく必要があるため、音を追うことは比較的簡単ですが、ごまかしが効かない難しさがあります。
詩的で宗教的な調べ 第6曲『眠りから覚めた御子への賛歌』Franz Liszt

自由な発想のもとで作曲された、規模の異なる全10曲で構成されたピアノ作品集『詩的で宗教的な調べ』。
フランス、ロマン派の詩人アルフォンス・ド・ラマルティーヌの詩に感銘を受けて作られたとされるこの曲集の第6曲『眠りから覚めた子供への賛歌』は、フランツ・リストの同名の合唱曲をピアノ独奏用に編曲した作品です。
合唱曲をベースにしながらも、ピアノの音色の美しさを最大限に引き出すメロディーが盛り込まれており、変化に富んだ弾きごたえのある1曲となっています。
超絶技巧練習曲 S.139 第5曲「鬼火」Franz Liszt

世界でも圧倒的に難しいピアノ曲として知られている作品『鬼火』。
偉大な作曲家、フランツ・リストが作曲した悪魔のような作品です。
この作品の難しさはなんといっても、圧倒的な音数の多さにあります。
とにかく速弾きが多く、鍵盤の飛びも激しいため、上級者でなければ弾くことすらかないません。
表現力よりも、テクニックや持久力などの基礎的な部分が求められるタイプの作品といえるでしょう。
テクニックの限界に挑みたい方は、ぜひチャレンジしてみてください!