【フランツ・シューベルトの名曲】歌曲王が遺した珠玉のクラシック作品。おすすめのクラシック音楽
「魔王」「アヴェ・マリア」をはじめ600を超える歌曲を遺したことから、「歌曲の王」と称されるオーストリアの作曲家、フランツ・シューベルト。
シューベルトは、代表作とされる多くの歌曲はもちろん、ピアノ独奏曲や交響曲、室内楽曲などを幅広く手掛けたことでも知られています。
本記事では、そんなシューベルトの作品のなかでも特に人気の高い楽曲や、コアなクラシックファンらが好む隠れた名曲を厳選!
生涯にわたって作曲活動を続けた音楽家の魂がこもった、珠玉の作品をご紹介します。
- ロベルト・シューマン|名曲、代表曲をご紹介
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- 切ないクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- 【ベートーヴェン】名曲、代表曲をピックアップ!
- メンデルスゾーンの名曲|人気のクラシック音楽
- ヨハン・シュトラウス2世|名曲、定番曲をご紹介
- グスタフ・マーラーの名曲。人気のクラシック音楽
- 【モーツァルト】代表曲、人気曲をご紹介
- フランツ・リストの名曲。人気のクラシック音楽
- 【ロマン派の名曲】魂を揺さぶる珠玉の有名作品を一挙紹介!
- クラシックの名曲|一度は聴きたいオススメの作品たち
- Carl Maria von Weberの人気曲ランキング【2026】
【フランツ・シューベルトの名曲】歌曲王が遺した珠玉のクラシック作品。おすすめのクラシック音楽(111〜120)
即興曲集 第3番 変ロ長調 ,D935,Op.142Franz Schubert

19世紀初期のオーストリアを代表するフランツ・シューベルトの作品をご紹介します。
1827年に作曲されたこの曲は、主題と5つの変奏から構成される変奏曲形式で書かれています。
同じくシューベルト自らの作品の劇付随音楽からの引用を含む親しみやすい旋律が特徴的です。
各変奏では、付点リズムや装飾音、三連符などさまざまな技法が用いられ、ウィーン古典派の技巧とロマン派の叙情性が見事に融合しています。
シューベルトの作曲したピアノ曲の中では最も評価が高く、聴く機会も多いのがこの即興曲です。
ピアノを学び始めた方から中級者の方まで、シューベルトの世界に触れたい方におすすめの1曲です。
日本では東京電力のCMなどでも使用されているので、弾きながらこの曲だ!
と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
幻想曲 ハ長調 作品15 D 760「さすらい人幻想曲」Franz Schubert

フランツ・シューベルトの『幻想曲 ハ長調 作品15 D760』は、4楽章構成の高度なピアノ曲です。
シューベルト本人も上手く弾けず「こんな曲は悪魔にでも弾かせてしまえ」と言ったという逸話もあるそうで、とくに第4楽章の左手のアルペジオが演奏者を悩ませます。
しかし技巧だけでなく、深い音楽性も求められる作品。
シューベルトの情熱と技術が見事に融合した本作は、ピアノ演奏の真髄を体感したい方にもぴったりです。
フランツ・リストによる編曲版も存在するので、聴き比べてみるのもオススメです。
幻想曲 ハ長調 Op.15 D760「さすらい人幻想曲」Franz Schubert

ロマン派を代表する作曲家、フランツ・シューベルトが手掛けた作品。
1822年に作曲されたこの曲は、シューベルト自身の歌曲『さすらい人』の旋律を基にしています。
全4楽章で構成され、切れ目なく演奏される点が特徴的。
第2楽章では『さすらい人』の旋律が明確に引用されており、孤独や漂流感といったテーマが色濃く反映されています。
技巧的に極めて難易度が高く、シューベルト自身も「こんな曲は悪魔にでも弾かせてしまえ」と困難を感じたそう。
発表会の舞台でも聴き映えすること間違いなしの1曲です。
ピアノ経験を重ねてきた方にぜひチャレンジしてほしい名曲ですね。
幻想曲 ヘ短調 Op.103 D 940Franz Schubert

フランツ・シューベルトが亡くなる年に作曲したと言われる名作『幻想曲 ヘ短調 Op.103 D 940』。
単一楽章の作品なのですが、実際のところは全4楽章のような作品で、それぞれの部分に特色があります。
『さすらい人幻想曲』と似たような曲ということですね。
133小節からヘ音とホ音が半音で衝突する不協和音が現れるのですが、連弾でこれを表現するのが難しいため、最後のパートはしっかりと練習しておきましょう。
魔王Franz Schubert

フランツ・シューベルトが18歳のときに作曲した歌曲。
ゲーテの詩に感銘を受け、一晩で完成させたと言われています。
父親が魔王から逃げながら、病気の息子を抱えて夜道を馬で駆け抜ける様子を描いています。
ピアノの連打音は、まるで馬の走る様子や、親子の焦り、不安を表しているかのようで、魔王の誘惑、父親の必死さ、息子の恐怖が見事に表現されていますね。
1821年に初めて公演され、その後多くの歌手やピアニストによって演奏され続けています。
怖さと切なさが入り混じった独特の雰囲気は、ハロウィンにもぴったりですよ。
鱒Franz Schubert
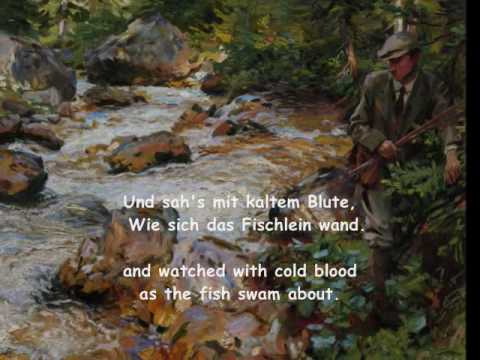
フィッシャー・ディースカウ、ジェラルド・ムーアによる名歌曲集に収録されています。
交響曲からピアノ曲にわたり幅広く作曲しましたが、特にドイツ・リートでは突出し、その質と量の高さから「ドイツ歌曲の王」と呼ばれています。
4つの即興曲 D.935, op.142Franz Schubert
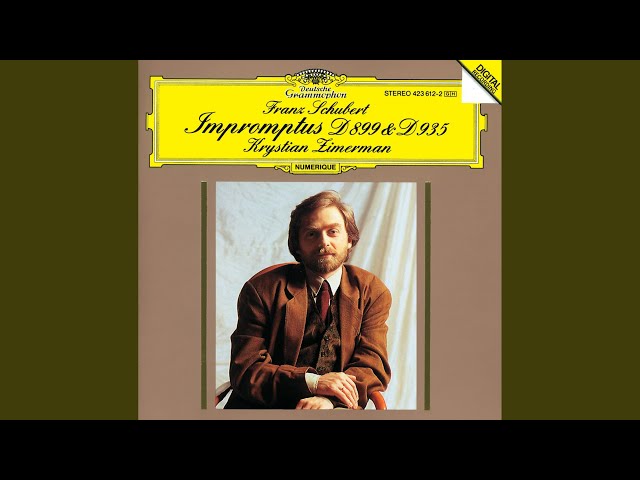
『ピアノ協奏曲 イ短調 作品54』は、シューマン作曲です。
激しいなかにもおだやかさがある曲です。
シューマンらしい、気品ある旋律に心を奪われてしまいそうな、素晴らしい協奏曲です。
チャイコフスキーや、有名なピアノ協奏曲とはまたひと味違う作品になっています。
聴き比べてみるのも楽しいと思いますよ。
ぜひ聴いてみてくださいね。






