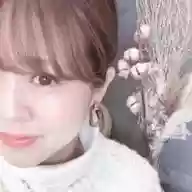【保育】夏のうた。楽しさいっぱい!夏の童謡&手遊び歌
梅雨が終わると、いよいよ夏がやってきます!
そこでこちらでは、夏を楽しむための童謡をいろいろご紹介します。
子供たちが大好きな歌や、保育園や幼稚園でよく歌われる手遊び歌も集めました。
童謡を聴くと、待ちになった夏がもっと楽しみになりますよ。
また、手遊び歌は小さな子供も楽しめるので、ぜひ保育に取り入れてみてくださいね。
暑い日が多くなりますが、童謡の中には聴くだけで涼しくなる曲もありますよ。
子供たちと一緒に、楽しい夏を一緒に楽しんでください!
- 7月に歌いたい童謡。楽しい夏のうた
- 【8月に歌える童謡】夏に楽しめる子どもの歌&手遊び歌
- 【海の童謡】海をテーマにした楽しい子どものうた
- 夏っぽい曲まとめ。海、空など夏によく似合う曲
- 【七夕の童謡】楽しい手遊び歌&懐かしのわらべうた・民謡集
- 【6月の童謡】梅雨の季節にピッタリの楽しい手遊び歌&わらべうた
- 夏うたメドレー。夏を彩る名曲、人気曲
- 5月に親しみたい童謡&手遊び歌!新緑の季節にピッタリな歌
- 虫を歌った童謡・民謡・わらべうた
- 子供におすすめの夏ソング。J-POP・邦楽の人気ソング【2026】
- 子供が好きな歌で盛り上がる!思わず歌いたくなる心に残る名曲集
- 【ひまわりソング】暑い夏に元気をもらえる名曲&人気曲をピックアップ
- 食べ物を歌った童謡・民謡・わらべうた
【保育】夏のうた。楽しさいっぱい!夏の童謡&手遊び歌(111〜120)
浜辺の歌作詞:林 古渓/作曲:成田為三

ゆったりとしたワルツのリズムで紡がれる『浜辺の歌』は、1913年に発表された日本の代表的な叙情歌の1つで、2007年には「日本の歌百選」にも選ばれた名曲です。
名作映画『二十四の瞳』を鑑賞された方であれば、劇中で登場する女学生がこの曲を無伴奏で歌うシーンを思い出されるのではないでしょうか。
古い言葉が使われた歌詞を深く理解することは大人であってもやや難しいかもしれませんが、メロディの美しさはきっと幼い子どもたちにも伝わることでしょう。
シャボン玉作詞:野口雨情/作曲:中山晋平

日本が誇る唱歌や童謡の中でも、老若男女を問わず誰もが知っている名曲『シャボン玉』は、どこか切ないメロディも相まって日本人の心に響くものがありますよね。
暑い夏にこの曲を歌いながらシャボン玉遊びをすれば、少しは涼しい気持ちにさせてくれることでしょう。
余談ながら、この曲の物悲しさを感じさせる歌詞の意味については諸説あり、作詞を担当した野口雨情の生まれて間もなく亡くなってしまった長女への思いが込められたもの、というもっとも有名な説も実際に真実なのかどうかは定かではないとのことです。
あめふりくまのこ作詞:鶴見正夫/作曲:湯山昭

この曲は1962年にNHKで放送された童謡です。
大人のクマは迫力がありますが、子供のクマはコロコロとしてキュートですよね。
この曲はそんな子供のクマが雨の日に小川にやってきて、水を救って飲んだり、魚が来ないかとずっと小川を眺めている様子が歌われます。
なかなか魚が来ないので、葉っぱを傘にしてみたりと頑張る姿が愛らしいです!
いわしのひらき
イワシ、ニシン、サンマ、サケと食卓に並ぶお魚ですが、お子さんによってはお魚はハズレのメニューでしょうか?
お魚のひらきの手遊びソングがこちらで「ズンズンちゃっちゃ」というリズムがとても楽しげです。
楽しい歌からお魚にも興味を持ってもらえそうです。
そしてこの曲の目玉は、最後に登場する大きな魚(?)です。
ひらきにしたら大変なことになりそうです。
それが一体何かは曲で確認してみてくださいね!
そーめんつるつる
暑い夏の日の定番メニューといえば素麺!
ゆでて水でしめるだけというお手軽さもありつつ、ツルンとサッパリした素麺は愛されメニューです。
そんな素麺を歌ったこの曲は、素麺のツルツルした食感を手遊びもまじえて楽しく表現しています。
食べ終わったとに涼しい気持ちになるところ表現されていてかわいい曲です!
1回聴けば覚えてしまいそうな簡単なメロディもポイントですね!
牧場の朝作詞:文部省唱歌/作曲:舟橋栄吉
爽やかな夏の朝を思わせるような曲『牧場の朝』。
福島県にある牧場をモデルに作られ、牧場がある鏡石町の町歌にもなっています。
最初に発表されたのは1932年で、その後1968年にNHKの『みんなのうた』で放送されました。
タイトルの通り、朝の牧場の光景が描かれた歌詞はとてもリアルで、自分がそこに立っているような感覚になります。
夏は朝といえども暑い日が多いですが、曲から爽やかな夏の朝を感じてみるのもいいかもしれませんね。
お子さんにとっては、牧場がどんなところか想像するきっかけになりますよ。
羽衣作詞:林柳波/作曲:橋本国彦

1941年から親しまれるこちらの童謡は天女の白くてフワフワとした美しい羽衣がモチーフです。
そこに夏の涼しげな浜辺や、雲のかかった富士山など日本の夏の美しい風景が重ねられています。
とても幻想的なイメージがふくらみますね。
ちなみに「文部省唱歌」というのはこの曲が作られた当時、文部省の検定を通過した児童向けの歌唱推薦曲のことです。