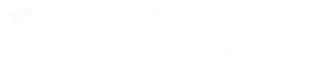【すぐ遊べる!】小学生にオススメの盛り上がるレクリエーションゲーム
みんなでわいわい楽しい小学生が盛り上がるレクリエーションゲーム!
教室でも体育館でも、みんなで笑顔になれる遊びはいろいろありますよ。
そこで、こちらではチーム対抗で協力できるゲームや、頭を使うひらがなクイズ、体を動かすボール鬼ごっこまで、道具を使わないでできるものから簡単な準備で楽しめるものまで、楽しいアイデアをご紹介します。
友達同士の絆が深まったり、新しい一面を発見できたりするので、ぜひゲームを通して友達との時間を楽しんでくださいね!
- 【小学校】すぐ遊べる!低学年にぴったりの室内レクリエーション
- 小学校・高学年におすすめ!盛り上がる室内レクリエーション&ゲーム
- 小学1年生から6年生まで楽しめる遊びアイデア【室内&野外】
- みんなでできる遊び・ゲーム。楽しい遊びのアイデア集
- 【子供会】簡単で楽しい室内ゲーム。盛り上がるパーティーゲーム
- 小学生のお楽しみ会が大盛り上がり!室内ゲームのアイデア集
- 雨でも安心!体育館でできる楽しいレクリエーション
- 【盛り上がる!】学校の教室で遊べる簡単ゲーム。クラスで楽しむレクリエーション
- 室内で楽しめる簡単なレクリエーション・ゲームまとめ
- 【子供向け】本日のおすすめレクリエーションアイデア集
- 【小学校レク】お楽しみ会におすすめのゲーム・出し物
- 子供向けのレクリエーション人気ランキング
- 学童保育で大活躍!道具なしでできる集団遊び&ゲームのアイデア特集
じゃんけん・そのアレンジゲーム(11〜20)
ドンパッパ

じゃんけんからの派生ゲームです。
かけ声に合わせてじゃんけんの手を出し合ってあいこになるまで続け、あいこになった瞬間に先に決められたかけ声を発した方の勝ちです。
地域により名称やかけ声が異なっているので、それを確かめ合っても面白いですよ。
進化じゃんけん

シンプルなのに盛り上がる!
進化じゃんけんのアイデアをご紹介します。
じゃんけんで勝敗を決めて遊ぶだけではつまらない!
という小学生の皆さんにオススメしたいアイデアです。
ゴキブリからスタートして、カエル、ウサギ、サル、人間と進化しながら遊ぶゲームです。
同じ進化形態同士でじゃんけんすることと、いきものになりきったポーズや動きをすることがこのゲームのポイントです。
遊びに慣れてきたら、子供たちと一緒に進化するいきものを考えてみるのもおもしろそうですね。
心理じゃんけん
@cocoskip♬ オリジナル楽曲 – ゆず(๑′ᴗ‵๑)♪ – ゆず(๑′ᴗ‵๑)♪
新感覚の見えないじゃんけん!
「心理じゃんけん」のアイデアをご紹介します。
このゲームは向い合った状態で、お互いの手元が見えないように壁をへだててじゃんけんをします。
「私は◯◯を出しています」「◯◯を出していますか?」など、会話をしながら相手の出しているものを予想しましょう。
制限時間が来るまでは出したものを変えることも可能です。
制限時間が来たときに、どっちが勝っているのでしょうか!
ハラハラドキドキしながら楽しめるアイデアです。
新聞紙を使ったじゃんけんあそび
@toiro_efilagroup どこまで耐えられるかな?? #新聞紙#じゃんけん#療育#遊び#放課後等デイサービス#toiro#神奈川
♬ オリジナル楽曲 – toiro(トイロ)放課後デイ – toiro(トイロ)放課後デイ
勝敗を可視化しながら遊べる!
新聞紙を使ったじゃんけんあそびのアイデアをご紹介します。
じゃんけんをしていると、周囲の勝敗が気になることもありますよね。
今回は、勝敗を可視化するために新聞紙を使って遊んでみるのはいかがでしょうか?
じゃんけん以外の動作が増えることによって、子供たちの遊びへの興味も増していきそうですね。
広げた新聞紙の上に立ち、じゃんけんで負けたら新聞紙を折りたたんでいくシンプルなルールです。
海に浮かぶ船をイメージしたり、山にかかる橋をイメージしたりするのも盛り上がりそうですよ!
はしごじゃんけん

はしごの両端から両チームがスタート、出会ったところでじゃんけんをする「はしごじゃんけん」です。
負けた人は列の後ろにまた戻り、勝った人はそのまま進んで次の人とまたじゃんけんをして相手のスタート地点を目指します。
先に相手のスタート地点に着いたチームの勝ちです。
はしごはないと思うのでマスキングテープなどではしごを床に作ってもいいですよ。
協力型じゃんけんレク

隙間時間や休み時間に楽しもう!
協力型じゃんけんレクのアイデアをご紹介します。
じゃんけんといえば勝敗を決めるというイメージがありますよね。
今回は協力型じゃんけんでユニークな遊びにチャレンジしてみましょう。
動画の中では「じゃんけんピラミッド」と「チョキの女王」というゲームが紹介されていますね。
どちらも子供たちがチームで戦うゲームなので、クラスやグループの関係性を深めたい機会などに活用すると良いでしょう。
玉入れフープジャンケン

アイテムを使うと盛り上がる!
玉入れフープジャンケンのアイデアをご紹介します。
玉入れといえば、運動会や体育祭で使用する用具を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
今回は、室内で気軽に準備できるもので、玉入れフープジャンケンに挑戦してみましょう。
準備するものはカラーボール、小さめのフラフープです。
遊びの導入として、フラフープの中にボールを自由に入れて遊ぶ時間を設けると良いでしょう。
最終的には、グループの中のじゃんけんに勝利した人がボールを投げ入れる役を担うという遊びに展開していますね。
遊びをアレンジしながら取り入れてみてくださいね。