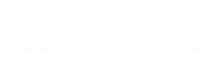小学生におすすめ!自由研究テーマ&工作アイデア
夏休みといえば、なかなか決まらないこともよくある自由研究のテーマ。
理科の実験や工作、どちらも楽しいですよね!
工作が得意な子供は、作る楽しみを感じながら進められるので工作がオススメです。
夢中で取り組むと、数日で完成できることもあります。
そこでこちらでは、自由研究や工作のアイデアをいろいろご紹介します!
もしテーマに困ったときは、ぜひ参考にしてみてください。
楽しい夏休みの思い出を作るために、自分だけの作品を作ってくださいね!
- 【夏休みの宿題に!】見たら作りたくなる 小学生向け簡単ですごい工作
- 簡単だけどすごい工作。小学生が作りたくなる工作アイデア
- 【小学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- 小学生の男の子が夢中になる自由研究工作!身近な材料で作れるアイデア
- 【小学校高学年向け】簡単だけどすごい!夏休み工作のアイデア集
- 高学年男子向け!簡単だけどすごい工作【手抜きとは言わせない】
- ストローを使った楽しい工作
- 小学生の低学年にオススメ!身近な材料で作るペットボトルの工作アイデア集
- 簡単かわいい自由研究工作!作りたくなる女の子向けのアイデア集
- 【中学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- ダンボール工作で作るおもちゃ!作って遊べる本格アイデアも
- 【簡単だけどすごい!】高学年の女子向けの工作アイデア
- 親子で楽しめる工作。子供の暇つぶしにおすすめの工作アイデア
低学年向け(81〜90)
宝石箱みたいな万華鏡

万華鏡を作る、となるととても時間もかかりそう、むずかしそう、と思ってしまいますよね?
ですがこの作り方は、家にあるものですぐにできちゃうすごいアイデアです。
筒状のお菓子の空き容器のフタの部分に穴を空け、そこから光を取り込みます。
ただ丸に開けるのではなく、お花型などに開けるとよりキレイになりますよ。
穴の上にセロハンテープを貼り、上から油性ペンで色を塗ります。
筒には黒のガムテープを巻き、そしてフタとは反対側にプチプチを貼ります。
プチプチにも色を塗ればカラフルで楽しい万華鏡が完成です!
石アート

夏休みの自由研究や工作にオススメの石アート。
川遊びやキャンプで石を拾ってきたら、ぜひアート作品に仕上げてみましょう!
フレームの上に木の枝や石をお好きなようにレイアウトして、石用接着剤で固定するだけ!
石と組み合わせる素材もナチュラルなものを選ぶと、オシャレな雰囲気に!
お子さんの自由な発想が楽しいアートに仕上がるのではないでしょうか。
お子さんとの思い出作りにもぴったりなので、ぜひ夏休みに親子で工作を楽しんでくださいね。
メラミンスポンジのサンドウィッチ工作
@picoton_craft スポンジでサンドイッチづくり♪ #簡単工作#親子工作#工作#子どものいる暮らし#サンドイッチ
♬ オリジナル楽曲 – ピコトン/工作クラス – ピコトン🐥100均簡単工作
思わずピクニックに持っていきたくなる、おいしそうなサンドウィッチをメラミンスポンジで作ってみるのはいかがでしょうか。
作り方はとっても簡単!
まず大きめで厚みのあるメラミンスポンジを用意し、サンドウィッチの形をイメージして三角にカットします。
中に具材を挟めるようにカッターで切り込みを入れましょう。
次にハムやレタス、スパゲティなど挟みたい具材を画用紙や毛糸で作ります。
カラフルな色合いを意識して具材を用意すると仕上がりもかわいくなりますよ。
最後に作った具材をサンドウィッチに挟めば完成です!
いろいろな具材を作って遊んでみてくださいね。
おもしろ百面相

絵を描くのが大好きな人、ゆっくりお絵画きをする時間がある人にオススメなのがこの「おもしろ百面相」です。
四角く折りたたんだ紙を広げてゆくと表情がどんどんと変わるといったもの。
笑った顔、泣いた顔、怒った顔など何種類かの顔を描いてくださいね。
顔は学校の先生やお友達の顔でもOK!
うさぎやネコなど好きな動物でもいいですよ。
大きな紙で作ればちょっとしたお面にもなりそうです。
イラストを描くのがメインとなりますのでぜひ楽しみながら作ってくださいね!
しっぽがゆれる貯金箱

夏の自由研究の定番といえば「貯金箱」。
ゆうちょ銀行が行っている「ゆうちょアイデア貯金箱コンクール」も有名ですよね。
「アイデアも出しつくされたのかな?」と思いながらも毎年たくさんのアイデア貯金箱が登場します。
そこで、「しっぽがゆれる貯金箱」をご紹介。
簡単な仕組みは、硬貨を入れたその重みでしっぽがゆらゆらと動く簡単なもの。
この仕組みを広げれば、魚釣りや恐竜の首などにもアイデアを転用できそうです。
乾くと色を塗れる紙粘土で作るのがオススメです!
キッチンでかわいいクラフト

学研から出版されている『小学生のキッチンでかわいいクラフト』という本をご存じですか?
おもしろい工作のアイデアがたくさん掲載されている本で、夏休みの自由研究や工作に使えそうなアイデアもたくさん載っているんですよ。
そこから1つ「紙のトームカップ」をご紹介。
簡単な流れは「水風船にノリを塗って和紙やちり紙でそれを包み、乾いたらその風船を割る」といったもの。
時間もそれほどかかりませんので時間に余裕がない方にもオススメですよ。
低学年向け(91〜100)
ストローで作れるサッカーゲーム

家の中で気軽にサッカーが楽しめるおもちゃをストローで作ってみるのはいかがですか?
友達や家族と楽しく夢中になりながら一緒に遊べますよ!
空き箱やストローなど身近な素材を使って作れるのも嬉しいポイント。
空き箱でコートを、ストローでゴールをそれぞれ作り、空き箱を切って作った選手にストローを付けて操作しながら遊びます。
好きな選手をイメージしながら似せて作ってみるのも盛り上がりそうですね!
子供たちの手先の器用さや集中力を育んでくれること間違いなしのこちらのおもちゃ、詳しい作り方は動画で紹介しているので参考にしながらぜひ作ってみてくださいね!