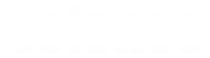小学生におすすめ!自由研究テーマ&工作アイデア
夏休みといえば、なかなか決まらないこともよくある自由研究のテーマ。
理科の実験や工作、どちらも楽しいですよね!
工作が得意な子供は、作る楽しみを感じながら進められるので工作がオススメです。
夢中で取り組むと、数日で完成できることもあります。
そこでこちらでは、自由研究や工作のアイデアをいろいろご紹介します!
もしテーマに困ったときは、ぜひ参考にしてみてください。
楽しい夏休みの思い出を作るために、自分だけの作品を作ってくださいね!
- 【夏休みの宿題に!】見たら作りたくなる 小学生向け簡単ですごい工作
- 簡単だけどすごい工作。小学生が作りたくなる工作アイデア
- 【小学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- 小学生の男の子が夢中になる自由研究工作!身近な材料で作れるアイデア
- 【小学校高学年向け】簡単だけどすごい!夏休み工作のアイデア集
- 高学年男子向け!簡単だけどすごい工作【手抜きとは言わせない】
- 【男の子向け】ペットボトルキャップを使った工作アイデア
- ストローを使った楽しい工作
- 小学生の低学年にオススメ!身近な材料で作るペットボトルの工作アイデア集
- 簡単かわいい自由研究工作!作りたくなる女の子向けのアイデア集
- 【中学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- ダンボール工作で作るおもちゃ!作って遊べる本格アイデアも
- 【簡単だけどすごい!】高学年の女子向けの工作アイデア
低学年向け(111〜120)
いろいろな液体に氷を入れてみよう

いろいろな液体に氷を入れてみるというのはいかがでしょうか?
意外な結果になるので、大人から子供までワクワクしながら一緒に楽しめますよ。
まずプラスチックコップを複数用意し、それぞれに液体を入れていきます。
水、サラダ油、牛乳、アルコール水などがいいでしょう。
次にそれぞれのコップに氷を投入します。
すると浮く氷と沈む氷に別れるはずです。
なぜそうなるのか一緒に考えてください。
また、溶けるまでの速さを計測してみても発見があるかもしれません。
アメをつくろう

木村拓哉さんや木村祐一さん、料理のできる男性ってかっこいいですよね。
ここはひとつ料理のできる男の子なら、アメ作りにチャレンジしてみましょう!
基本のアメだけなら材料は砂糖250gと水80mLだけでOKです。
材料を鍋に入れて中火で10分ほど煮ます。
うっすらと色が変わってきたら鍋からおろしてヘラでゆっくり回します。
固まる前に好きな形のアルミカップなどに小分けにします。
冷えたものをアルミカップから外せば完成です。
果物のジャムや抹茶を加えればいろいろな味のアメが作れますよ。
各工程を写真に撮ってレポートに付けてくださいね。
アメ作りだけなら1時間もあれば大丈夫です。
火を使うので大人の人と一緒にチャレンジしてください!
スイスイ走る船

お風呂や水遊びで使える、船を工作してみましょう。
材料は、牛乳パック、トレイ、ストロー、輪ゴム3本。
必要な道具は、ハサミとセロハンテープ、ペンです。
この工作のポイントは、牛乳パックと輪ゴム、ストローを使って作るスクリューで、こちらが船の動力部分です。
スクリューができたらそれを本体となるトレイにくっつけるだけなので、低学年の子でも1人で作れますよ。
完成したら、ゴムに取り付けたストローをくるくる回して、水の上に浮かせて遊びましょう。
ビーズボールヘアゴム

ヘアゴムにビーズボールでアレンジを加えたものを作ってみましょう。
ヘアゴムをベースにしたアクセサリーなので、普段のファッションにも取り入れやすく、手軽にオリジナリティが出せるところもポイントですね。
手順はとてもシンプルで、ビーズをテグスでつなげていき、つなげたものをヘアゴムに固定すれば完成です。
ビーズの色や組み合わせを考え、かわいらしいアクセサリーを目指しましょう。
使用するビーズのサイズ、本体のヘアゴムの色などでもアレンジの幅が広がりそうですね。
リサイクルマークを調べよう

普段リサイクルマークを意識していますか?
なんとなく存在は知っているけれど、詳しくわかっていないという方も多いのではないでしょうか。
そこでこの機会に調べてみるのもオススメです。
実はリサイクルマークにもさまざまな種類があるんですよ。
また、地域によって異なるマークもあります。
まずは身近な物についているリサイクルマークを調べてみましょう。
加えてリサイクルの仕組みや分別の大切さについて調べてみるのもありです。
室温で溶けないアイスキャンディー

子供たちが大好きなアイス。
夏になると食べる機会も増えますよね。
そこでオススメするのが室温で溶けないアイスキャンディー作りです。
こちらはその名の通り、熱くても溶けない不思議なアイスキャンディーを作るというアイデア。
なぜ解けないのかというと、メインの材料に寒天を使うからです。
寒天は融点が高いので、夏の暑さ程度ではなかなか解けないという訳です。
いろいろな味や見た目のアイスキャンディーを作ってみても楽しいでしょう。
そしておいしく食べて、すてきな思い出を作ってください。
手ごねせっけん作り

手ごねせっけん作りを知っていますか?
まずせっけん素地を温めて粘土状にし、そこに色素を加えて色を付けます。
すると限りなく粘土に近い状態に仕上がります。
あとは粘土遊びをする時のように、好きな形にこねてみてください。
形を整えたら乾燥させて完成です。
動物や星形など、アイデア次第でどんな石鹸も作れてしまいますよ。
何か夏らしいものをモチーフにしてみるのも、自由研究らしくていいですね。
ちなみに匂いを付けたい場合は、精油を使うのがオススメです。